
◇◇「品確法と第三者検査」-01◇◇
◇◇◇ present by apssk
APSS・住まい研究所の 菊池 と申します。
「品確法で住まいは守れるか?」の第1回目です。
品確法の内容とは?
平成12年4月1に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
(通称:品確法)が施行されました。
この法律は、目的として「住宅の品質確保の促進」、「消費者が安心して
住宅を取得できる市場条件整備」、「住宅に係わる紛争処理体制の整備」を
挙げています。
| 品確法の目的と制度 |
|---|
| 目的 | 制度 |
|---|
| 「住宅の品質確保の促進」 | 「瑕疵担保保証期間の10年義務化」 |
| 「消費者が安心して住宅を取得できる市場条件整備」 | 「住宅性能表示制度」(任意活用) |
| 「住宅に係わる紛争処理体制の整備」 | 「住宅に係わる紛争処理体制の整備」 |
上記の目的を達成するために、この法律には2つの柱が創られました。
1つが「瑕疵担保保証期間の10年義務化」で、もう1つが「住宅性能表示制度」
(住宅に係わる紛争処理体制の整備)なのです。
1つ目の「瑕疵担保保証期間の10年義務化」は住宅供給者(工務店や
建設会社等)が、消費者(注文者や購入者等)に対して責任を持つ瑕疵
(欠陥部分)に対して、強制的に10年間の保証期間を義務付けたものです。
今まで、契約書で2年~5年の瑕疵保証期間が一般的であり、その期間
以後に欠陥部分が発見されても瑕疵の保証対象とならないのが通例で、
住宅の欠陥が新築後3年目以降に見つかる場合も多く瑕疵担保期間の短さが、
紛争の種にもなっていました。
この法律は、住宅の工事を請負った施工会社に、竣工後10年間の
瑕疵担保期間義務付を行なったもので、本年(2000年)4月1日より
実際に適用されています。
2つ目の「住宅性能表示制度」(住宅に係わる紛争処理体制の整備)は
注文者が住宅の施工者に対して求めることが出来る、住宅の性能で構造や耐火、
消音等の住宅の性能を共通の土俵に立って表示するルールを定めるもので、
大手住宅メーカーや中小工務店、大工程度の規模でも、対等に住宅の性能を
明らかにすることが出来る制度ですが、この制度はあくまでも「任意」に
活用されることとなっています。
ただし、この「住宅性能表示制度」に関する評価基準は評価機関の
整備等が必要であり、今年の秋以降になる予定です。
「瑕疵担保保証期間の10年義務化」は品確法第7章の瑕疵担保責任の特例
として、条文に記載され、新築住宅の取得後最低10年の瑕疵担保責任保証期間を
義務付けたことにが記述されています。
従来は、請負契約書で瑕疵担保期間を2年程度に定めることが多く、法律上では
契約書の保証期間が実際の保証期間になっていました。
3年目以後に構造的な欠陥が発見されても、施工会社に無料で修理を求めること
が出来ないことが多く、問題となっていたのです。
構造的な欠陥は修繕に費用がかかり、住宅の所有者に大きな負担がかかりました。
また、この修繕の費用の多さが、住宅の紛争を多くし、問題を複雑にする原因と
なっていました。
この短い責任保証期間(瑕疵担保期間)を10年に延ばすことによって、
欠陥の修繕を実際に責任のある施工会社に10年間は、やらせることが
出来るようになりました。
構造的な欠陥は3年目以降に発見されることも多く、今までは構造欠陥と
判かっても保証を求めることが出来ずに、そのまま放置されたり、
修繕の高額な費用を請求されて、結局ローンが増えたりしていました。
今回の品確法の施行により、本年4月1日より以後に新築住宅の供給を受けた
場合には、施工会社に瑕疵担保期間として10年間の義務が生じます。
この義務は、基本構造部分(構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する
一部の部分)に対して、引渡しの日から10年以内に欠陥(瑕疵)が発見された
場合には、無料で補修等をする責任を負わせています。
また、この瑕疵担保責任部分に関しては、工事契約の際に例え2年とか3年
などの瑕疵担保責任の期間を定めたとしても、その記載は無効となり、10年間は
義務として瑕疵担保責任が有効に働くことと定めています。
また、新築住宅に対しての瑕疵担保責任期間であり、新築後10年以内の住宅を
譲り受けた場合などは、対象外とされています。
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/sannsya/hinkaku1.html
最後に基本構造部分の具体的な内容を記述しておきます。
図は上記hpをご覧下さい。
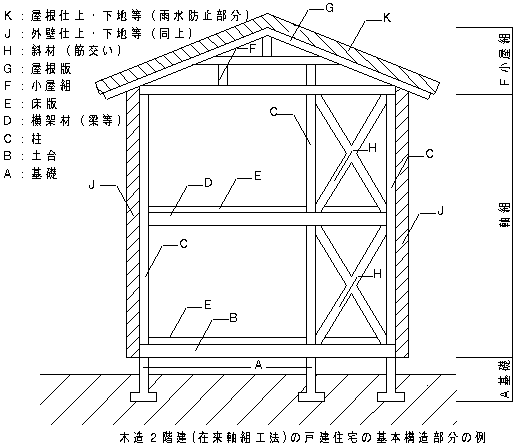
Ⅰ.構造耐力上主要な部分
A:基礎
B:土台
C:柱
D:横架材(梁材)
E:床版
F:小屋組
G:屋根版
H:筋かい
L:壁(構造用合板部分等)
Ⅱ.雨水の浸入を防止する一部の部分
J:外壁の仕上材及び下地材
K:屋根の仕上材及び下地材
以上が10年の瑕疵担保責任保証の範囲と考えられている部分です。
ありがとうございました。
次回も瑕疵担保期間の10年間の義務化関連の用語内容等についての予定です。
 このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問、ご依頼等がありましたら
このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問、ご依頼等がありましたら
apss設計までをお願いします。


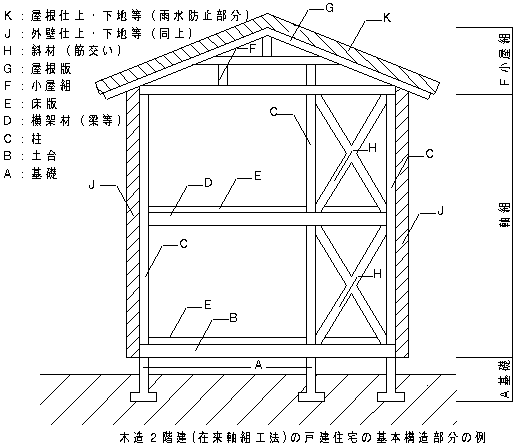
 このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問、ご依頼等がありましたら
このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問、ご依頼等がありましたら