 |
「4種類の換気」
| |
| |
| |
◆ 健康と住まい-38◆◆◆
◆◆
◆◆◆
◆◆◆◆ present by apss
朽木 醒(くちき あきら)と申します。
健康と住まいの38回目になりました。
38・機械換気と省エネルギー
☆ 前回はその前と2回に亘り断熱材と結露について、記述してきましたが、
簡単にまとめれば、断熱材は断熱性能と透湿抵抗を併せ持っており、
そのバランスの良い断熱材を使えば、問題なく良好な快適空間を得られます。
グラスウールウールや自然系繊維型の断熱材は透湿抵抗がほとんど無く、
透湿抵抗を補う部材との組み合わせが必要になるのです。
また、断熱材は温度の低い方にオープン(軽い材料にする)を使うのが、
建築物理の考え方に叶っている使い方ですが、夏冬共に空調を使う場合には、
温度の低くなる方向が屋外方向と室内方向の双方向となるので、
断熱材と補助部材の使い方が難しくなり、専門家との相談が必要になるのです。
詳しくは、下記をご覧ください。
前回の断熱材の内容No.37を見る。
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/meru/kenmeru37.html
今回の本題です。
☆01 換気の機能は、室内環境の維持!
換気の効用は、空気の浄化、脱臭、除湿、室温調節など、沢山あるが、
空気中に放散されたVOC(放散性化学物質)の除去も同時に行うことが出来るため、
換気を使って室内空気の浄化を行うのが、効率的で効果が高い方法と言えます。
健康住宅や安全住宅を謳い文句に、壁紙や漆喰、珪藻土の壁がもてはやされていますが、
厚さ1~3mm程度の材料では、汚染物質の吸着力や分解能力はたかが知れています。
効果があるものもありますが、吸着するにしろ分解するにしろ、
それらの壁が長期的な効果を保つ為には、換気による再生や浄化が必要になります。
健康素材は、実質の量的なものが少なく(ほとんど高価な為)また、
影響を及ぼす範囲も壁から数mm程度をカバーするのが、やっとの状況です。
それに比べると、床下に敷く活性炭や調湿炭は効果が期待できます。
換気による通気は必要ですが、ボリュウムが多いため、
一日のサイクルの中で寒いときには、空気中の相対湿度が高くなるので、
湿気を吸着し、昼間の暖かくなったときに湿気を放出する機能が働くためです。
化学物質の除去も、湿気の吸放出と共に行いますので、炭の量の多さが効果を発揮し、
床下を乾燥させるとともに、汚染物を取り除きます。
したがって、床下調湿炭等は、最低限のボリュームが必要であり、
量が確保されることで、調湿や浄化の機能を発揮できるのです。
昔の「住まい」が、調湿や浄化の機能を持っていたのは、
露出した柱や梁の木材があり、小舞竹を芯とした小舞壁(土壁)や
床下の土に埋め込まれた調湿炭など、呼吸する多量の部材があり、
部屋や床下、小屋裏を吹き抜ける風が常時あったからなのです。
現在の「住まい」はどの材料も薄い板状の部材であり、ボリュームがありません。
柱や梁は量的には十分ですが、壁の中や床下、小屋裏に隠れていて、
両側を結ぶ通気が無いため実際の役には、立たなくなっているのです。
したがって、室内の空気の調湿と浄化の為には、
室内の空気を使った、常時換気が最適で合理的な方法なのです。
そこで、壁中や床下、小屋裏にある柱、梁、補助部材の機能を生かす為には、
これらの部分にも通気が必要ですし、折角ある「住まい」の財産を生かす為にも、
床下や壁の中、小屋裏までも換気して、湿度の調整と空気の浄化、
さらに熱量を保存することが、室内環境の改善と、
建物自身の環境維持につながり、耐久性が昔の建物同様に向上するのです。
☆02 換気は4方式あり、特徴を生かした使い方が必要!
換気方式は第1種(強制給排気型)、第2種(強制給気+自然排気型)、
第3種(自然給気+強制排気型)、第4種(自然給排気型)の4方式があります。
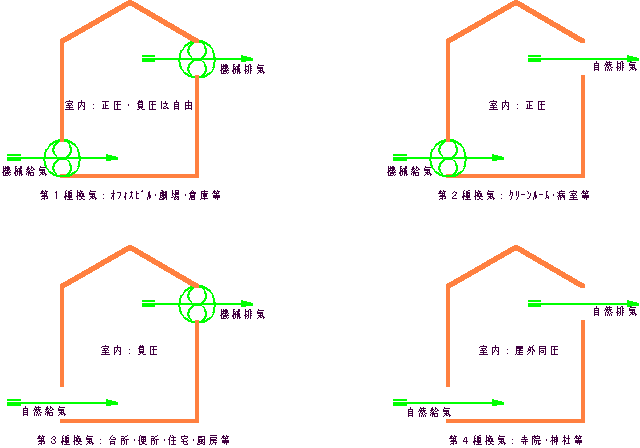
図-kannki01:4種類の換気
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/meru/kenmeru38.html#kannki
第1種換気(強制給排気型)は、換気扇により吸気と排気をそれぞれ独立して行うもので、
給排気の量のバランスにより、室内を正圧(+圧)にも負圧(-圧)にもできます。
換気をするのに、一番確実な方法ですが、イニシャル、ランニング両費用共に高くなりますので、
空調との共用や汚染空気が多く排出される場所に使います。
オフィスビル、劇場、ホール、屋内駐車場、ボイラー室、
厨房、倉庫などです。
第2種換気(強制給気+自然排気型)は、換気扇で強制給気をし、
排気は自然に換気口より排気する方式です。
室内が正圧(+圧)になるので、汚染空気の流入を避ける部屋に使うのが適しています。
例としては、クリーンルーム、病院の病室、手術室などがあります。
第3種換気(自然給気+強制排気型)は、給気口からの自然給気をし、
排気は換気扇により強制的に換気する方式で、室内は負圧(-圧)になります。
トイレや浴室などの汚染室からの汚染空気の流失をふせぎながら、換気する方法で、
「住まい」の換気にも基本的には、この第3種換気が使われます。
厨房や洗面所、その他には埃やチリが出る工作工場等に適しています。
第4種換気(自然給排気型)は、今までの「住まい」と同じで、
換気扇を使わずに換気をする方式です。
ただ、隙間面積が近頃の「住まい」では少なくなっていますので、
給気口と排気口を設けて温度差と気圧差で換気するのですが、
建築基準法の改正により2003年6月より、住宅では強制換気が
義務付られましたので、特殊な場合を除いて、自然給排気方式は使えなくなりました。
☆03 「住まい」の気密性はどこまで必要か。
最近、高気密・高断熱住宅が注目を集めています。
高気密はほとんどプラスチックフィルムに依存している工法が多く、
自然素材派からは、空気の流通が悪い「住まい」のように言われています。
実際にも外部の空気が、自由に入ってくることはありませんが、
空調の為の省エネや換気を効率よく行う為、そして結露の防止も出来、
昨今重要な工法になっています。
2000年に次世代省エネルギー基準が示され、気密性能もその値が出されています。
北海道・東北で高気密性能C=2C㎡/㎡、その他の地域で高気密性能C=5C㎡/㎡、
となっています。(この値をC値と言います)
空調の効率や省エネ、換気の効果を考慮した場合、当然気密性能が必要になります。
一部のハウスメーカーなどのように、高気密性能で、C値を0.1や0.2の上昇を争う
必要はありませんが、次世代省エネルギー以上の高気密性能は必要です。
この基準は品確法の熱の基準と比較しても同等ですが、
それほど厳しい基準値ではなく、高気密住宅としてはもう少し上の、
北海道・東北で高気密性能C=1C㎡/㎡、その他の地域で
高気密性能C=3C㎡/㎡程度を、目標したほうが良さそうです。
☆04 空気齢でも的確な換気が快適性をもたらす。
空気には空気齢との考え方がある。外部から直接入ってきた空気が新しい空気であり、
室内で使われ、徐々に汚染され最後に捨てられることから考えられた基準です。
空気齢が若い空気は、外部の空気と同等の新鮮な空気で、人の呼吸や、
塵に汚染され、最後に厨房レンジの酸素供給として役に立ち、
その後外部に捨てられることになります。
空気は室内に長く滞留すると、自然と汚染されますので、
外気の方が、空気が綺麗だとの前提にたって換気法は考えられています。
屋外の空気は綺麗ですので、なるべく屋外の新しい空気を居間や寝室から取り入れ、
まず最初に人に供給し、徐々に汚染室を経由して、
室内を浄化しながら「住まい」の健康にも役立つように空気を通し、
その後排出されるように計画されるのが、空気本来の流れとなります。
したがって、汚染された空気を使う場合には、負圧にして使う必要があります。
換気方式のうち、第1種か第3種を使って計画をするのがよいのです。
☆05 換気のエネルギーロスは高気密でも一般でも変わらない。
高気密・高断熱住宅の省エネルギー度合いは、一般的な住宅に比べ、
38%程度で済むのですが、その中で換気によるロスが占める割合は、20%程度です。
換気量は一般住宅でも高気密住宅でも、同じように(0.5回/h以上)必要になります。
したがって、換気による省エネはほとんど出来ないことになります。
換気で捨てる熱エネルギーを有効に使おうとすると、
熱交換機を使うか、「住まい」自体に熱を蓄えるか、しか方法はありません。
熱交換機は電気エネルギーを使い、フィルター交換が必要であり、
熱の交換量を多くする為には、全熱交換をする必要があります。
全熱交換は水分も交換されるため、交換機の汚れが酷くなったり、
臭いが残る可能性も高くなり、あまり省エネとは言えません。
換気による熱を「住まい」の、基礎や木材に蓄え、
年間サイクルで熱を、使うようにするのが、
換気に対する無駄のない省エネの考え方です。
今回は以上です。
「外断熱スパイラルエアーシステム住宅」のページです。
apssのhp参考にしてください。
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/kennkou1.html
ありがとうございました。
 このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は
このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は
apss設計までをお願いします。


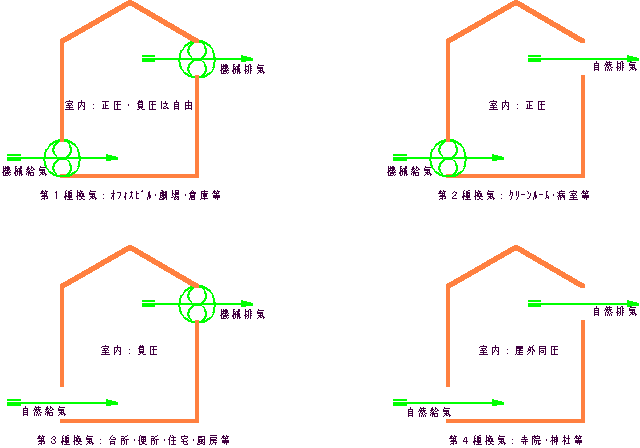
 このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は
このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は