 |
「スェーデンハウスの、結露推定図冬」
「フィンランドの住宅・結露推定図冬」
「スェーデンハウス・内断熱工法・フィンランドの住宅・結露推定図夏」
| |
| |
| |
◆ 健康と住まい−37◆◆◆
◆◆
◆◆◆
◆◆◆◆ present by apss
朽木 醒(くちき あきら)と申します。
健康と住まいの37回目になりました。
37・断熱材は温度の低い方にオープンに使う
☆ 前回にひき続き断熱材と、結露の関係ですが、グラスウールは北国向きの断熱材、
と考えた方が良いのかもしれません。
☆01 グラスウールは単独では使い難い!
住宅の現場では、相変わらずグラスウールを断熱材として、使用している割合が多く、
一戸建の60%以上はグラスウールを断熱材として使用しています。
北欧から使い始められた、このグラスウールの断熱材ですが、
相変わらず北欧で一番使われている断熱材は、グラスウールで、
使われる場合は単独では使われず、常に防湿シートと共に、使われています。
前回でも述べましたが、グラスウールを内断熱(充填断熱)に使いますと、壁内結露の恐れが
非常に高くなります。
これは、断熱抵抗と透湿抵抗のバランスの悪さが引き起こす問題なのです。
グラスウールは断熱抵抗はとても高いのですが、透湿抵抗は無いに等しい性能ですので、
断熱抵抗(性能と考えてよい)で、温度を下げたとしても、湿度を下げることが出来ない為、
温度は低いが、湿度の高い部分がグラスウールの中に出来てしまうのです。
水蒸気理論とは温度と湿度との関係を、論理的に解き明かしたものですが、簡単に説明すれば、
冬のガラス窓の結露や夏の冷たい水の入ったグラスの結露の理由を考えたものなのです。
冬のガラス窓の結露は、室内の湿度が低くてもガラス窓が低温ですと結露します。
冬の寒さで窓のガラスが低温になると、ガラス窓附近の空気は冷やされますが、
湿度は室内は均一であり、窓附近の空気が結露点以上に冷やされると、
温度の低い空気は水蒸気を含む量が少なくなる為、余った水蒸気は水滴になり、
温度の低いガラス窓に付着し結露となるのです。
前回の内断熱の結露推定グラフ図−Uchi1をもう一度見てください。
赤い線は水蒸気の露点温度ですが、透湿抵抗の低い、グラスウールの中で結露が現れる
ことを示しています。
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/meru/kenmeru36.html#uchidannnetu1
グラスウールの外に構造用合板12mmがありますが、その合板の透湿抵抗が高いため、
合板により水蒸気はブロックされ、外に出ないので、合板の外側では結露にならないのです。
合板の隙間が多い場合に、室内の空気が出て行けば、やはり結露の危険性があります。
ただ、合板の外部側に外壁通気路があると、通気によって水蒸気は放散されますので、
結露には至りませんが、室内側の温度の高い空気が、防湿層もなく、壁の中に停滞すると、
結露の可能性がとても高くなり、危険な状態になるのです。
☆02 北欧の断熱工法はどうなっているのか。
下記の図は、スェーデンハウスの、結露推定図です。
(下記をクリックすると「スェーデンH・結露推定グラフ冬」が出ます。)
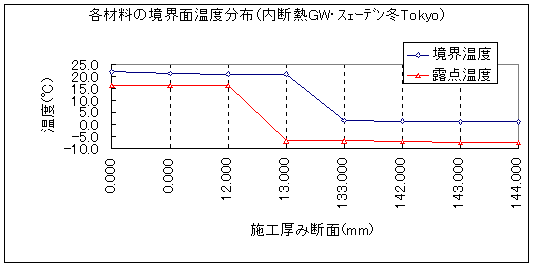
図−sweden-1:スエーデンH・内断熱GW・結露推定グラフ冬
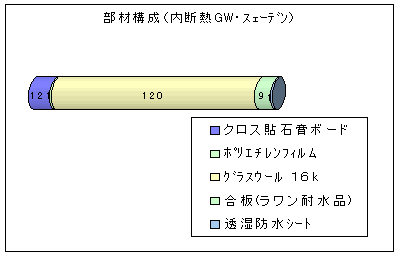
図−sweden-2:スエーデンH・内断熱GW・壁部材構成
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/meru/kenmeru37.html#sweden
スェーデンハウスの場合、防湿・気密層として0.2mm程度の樹脂フィルムを、
室内側のPB(石膏ボード)の裏に張り込んでいます。
その他の壁の構成は、GW120mm、耐水構造用合板9mm、透湿防水シート、通気層、外壁
との構成で、断熱材にグラスウール使用の内断熱住宅とほとんどかわりません。
防湿・気密の樹脂フィルムは断熱抵抗はほとんどありませんが、透湿抵抗は非常に高く、
水蒸気も空気もほとんど通さない性質をもっています。
この防湿・気密フィルムを室内側に張り巡らせることで、水蒸気が壁の中に出なくなり、
部材の境界温度と水蒸気量のバランスが取れるようになります。
このように断熱抵抗と透湿抵抗のバランスが、壁の中で取れるように、
材料の使い方を研究するのが、建築物理であり、水蒸気理論なのですが、
この考え方を取り入れて、設計を考えているところが、
ハウスメーカーや工務店にもまだ少ないのです。
もう一つ例としてフィンランドの住宅の場合を見てください。
下記の図は、フィンランドの住宅・結露推定図です。
(下記をクリックすると「フィンランドの住宅・結露推定グラフ冬」が出ます。)
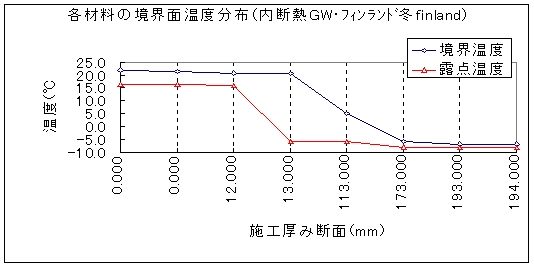
図−finland-1:フィンランドの住宅・内断熱GW・結露推定グラフ冬
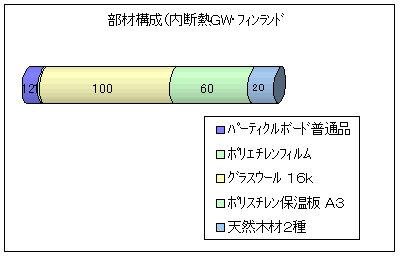
図−finland-2:フィンランドの住宅・内断熱GW・壁部材構成
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/meru/kenmeru37.html#finland
フィンランドの、あるメーカーで建てる仕様そのままですので、
室内環境は、これまで例に出した冬の住宅と同様の設定とし、
外気温等はフィンランドの気候に合わせて設定しています。
フィンランドの住宅の壁構成は、室内側から、クロス+パーティクルボード12mm、
防湿気密フィルム、GW100mm、ポリスチレン板60mm、外壁天然木板20mmとなっています。
結露推定グラフ、図−finlandは青線の断熱抵抗による境界温度と、
赤線の透湿抵抗による露点温度が、平行線に近い折線グラフになり、
フィンランドの住宅でも、防湿気密シートの効果が示されています。
フィンランドの住宅の場合は、、防湿シートの特徴をより強く表しています。
防湿シートで水蒸気のほとんどを抑えており、結露点以下の少ない水蒸気が少し漏れて、
断熱材のGWやポリスチレンに達しますが、すでに結露点以下の水蒸気量のため、
水蒸気を含んだ空気が冷やされても、結露を起こすことが無いのです。
スェーデンHや、フィンランドの住宅の場合、冬は外気の平均で-7℃ほどになりますが、
夏は、16、17℃ですので、冬の寒さだけを対象に、断熱も考えれば良いのです。
しかし、我が国では夏の暑さの対策も考えなければ、なりません。
まして、関東以西においては、冷房は住宅でも必需品になっています。
それでは、スェーデンHやフィンランドの住宅を東京近辺の夏の状態においてみましょう。
☆03 北欧の断熱工法で、日本の夏を過ごすとどうなるか。
下記の図は、スェーデンHやフィンランドの住宅で東京の夏に過した時の、壁の中の状態を、
これまでと同様にグラフで示します。
(下記をクリックすると「スェーデンH及びフィンランドの住宅・結露推定グラフ夏」が出ます。)
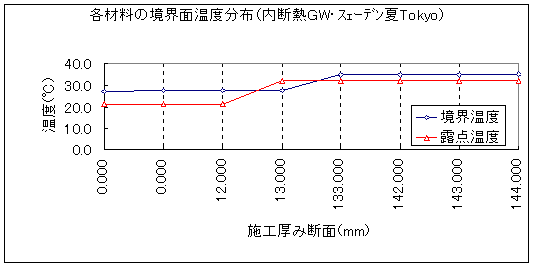
図−swedensum-1:スエーデンH内断熱GW・結露推定グラフ夏
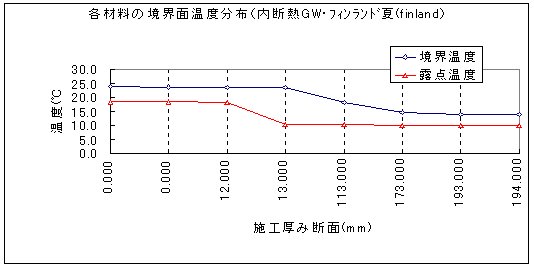
図−finlandsum-1:フィンランドの住宅の内断熱GW・結露推定グラフ夏
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/meru/kenmeru37.html#swedensummer
スェーデンHとフィンランドの住宅を壁構成は同じ仕様で、
スェーデンHは東京の夏に冷房を使った場合のグラフであり、
フィンランドの住宅はフィンランドでの夏の場合のグラフです。
スエーデンHも東京の夏に冷房を使っている状態にすると、
夏の逆転結露を起こす可能性を示しています。
青線の部材境界温度と赤線の露点温度とが、防湿・気密層のフィルムで交差し、
結露の可能性を示しているのです。
フィンランドの住宅をフィンランドの夏で過すようにすると、平均気温16、17度ですので、
冷房もいらず、したがって結露も全く心配ない状況をフィンランドの夏のグラフは示しています。
冬の暖房時も、夏の冷房時も結露の可能性を示さないようにするのには、断熱材や防湿材の
北欧の工法を真似するのではなく、バランスをよほど良く考えないといけないことを、
教えてくれています。
☆04 断熱材は温度の低い方にオープンに使う。
前回は内(充填)断熱と外(外張)断熱の結露の可能性について、
今回は、北欧の断熱工法について、見てきました。
これらの、内容や今までの研究により、断熱材の基本的な使い方を示します。
「断熱材は温度の低い方に向かって、透湿抵抗の高いものから低いものへと使う」のです。
このような、基本的な断熱材の使い方が、ほとんどの書物や研究書でも示されていません。
これは、断熱材それ自体の性能や工法ばかりに、考え方が偏っていたからだと思われます。
様々な断熱材の性能や価格を詳しく書き、別に結露の問題を記述している書物は、
沢山ありますが、断熱材と結露の関係を複合的に研究したものはほとんどありません。
しいてあげれば、南雄三氏の「高断熱・高気密バイブル」に断熱材は外にオープンに、
と記述されている程度です。
前回そして今回とグラフや壁の部材構成図を何点も表示し、断熱材と結露の関係を、
研究してきましたが、要約すれば「断熱材は温度の低い方にオープンに使う」なのです。
もう一度、前回からの内断熱と、スェーデンHのグラフを見てみましょう。
内断熱の場合、結露の可能性が高いグラフになります。
壁部材の構成は室内側より、PB(プラスターボード)12mm→グラスウール100mm→
構造用合板9mm→透湿防風シート→壁通気層→サイディングボート(外壁)
の順に並んでいます。
この部材を、透湿抵抗の高い順に並べると、構造用合板9mm→
PB(プラスターボード)12mm→透湿防風シート→グラスウール100mmの順になります。
夏のグラフを見ると、PBとグラスウールまでは順調ですが、構造用合板9mmの部分で、
急に透湿抵抗が高くなり、結露の可能性が高くなります。
外壁にモルタル仕上げを使うと、構造用合板9mm→防水紙→モルタルと外に向かうほど、
透湿抵抗が高くなるので、結露の可能性がより高くなるのです。
この結露状況を無くす為に登場してきたのが、防湿気密シートなのです。
北欧では、防湿シートなくしては建築できませんが、我が国でも北海道や東北では常識となり、
関東以西でも、高気密高断熱住宅では必ず使われているのが、防湿気密シートです。
スェーデンHやフィンランドの住宅でもお判りのように、室内側のPBの下に防湿シートを張り、
水蒸気を壁の中に放出しないようにし、防湿の役割を、このシート1枚で果しているのですが、
コンセントやスイッチ、照明器具や設備配管、給排気口など、穴を開ける箇所が多く、
精度の高い施工をするのは、かなり難しいのです。
しかし、この防湿気密シートがないと、結露の恐れがとても高くなりますし、省エネの為にも、
高気密高断熱住宅では、必ず必要となっていますし、施工の難しさを逆手にとって、
施工精度の良い、他には真似の出来ない住宅だと宣伝している、ハウスメーカーもあります。
しかし、あまりにも高い施工精度を必要とする施工は、故障や経年変化など、
問題を起こす確立が高くなることも、また避けられない事実なのです。
ほぼ、お判り戴けたのではないかと思いますが、冬だけを対象にした場合には、
防湿気密シートの使用だけで良いのですが、夏に冷房を使かう場合には、
室内が屋外より温度が低くなるので、断熱材や壁構成部材の並べ方も、
屋外より室内に向けて透湿抵抗の高いものから低いものへと並べるのが良いことになります。
夏には屋外から室内に向けて、透湿抵抗の高い順に並べると結露が出ないことは、
内断熱の夏のグラフが示しています。
したがって、GWのようなの断熱材を使うと断熱材に透湿抵抗がほとんど無い為、
夏には、逆転結露現象が起きる可能性が高いのです。
これらを解消する為には、樹脂発泡系の断熱抵抗と透湿抵抗とのバランスのとれた
断熱材を使うか、WGのような鉱物繊維系の断熱材の場合には、室内側に防湿気密シートを使い、
かつ防湿気密シートと断熱材との間に、室内側にも通気路を付、夏の逆転結露が起こる前に、
通気により水蒸気を排出する工夫をすることなのです。
植物繊維系の断熱材の場合には、断熱材自身が呼吸をし、水蒸気を吸収したり、
放出したりするため、結露の危険性から逃れていますが、長期的な観点に立ってみると、
室内側にも通気層を付け、常時部材が呼吸できる状態にしておくことが、
壁の中も乾燥状態にしておけるのです。
今回は以上です。
「外断熱スパイラルエアーシステム住宅」のページです。
apssのhp参考にしてください。
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/kennkou1.html
ありがとうございました。
 このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は
このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は
apss設計までをお願いします。


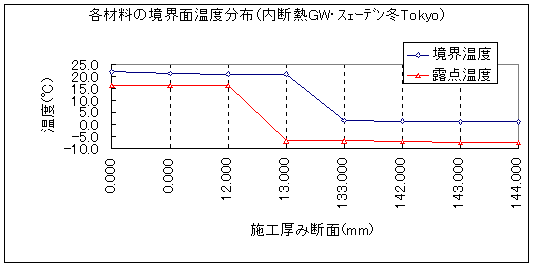
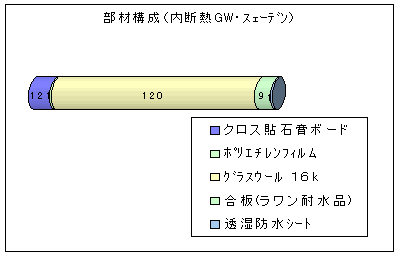
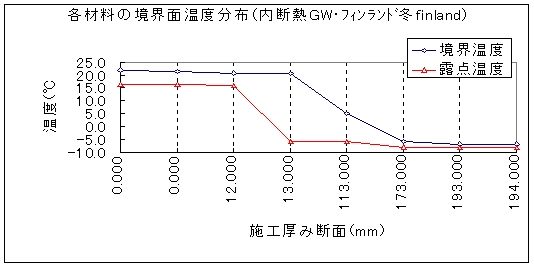
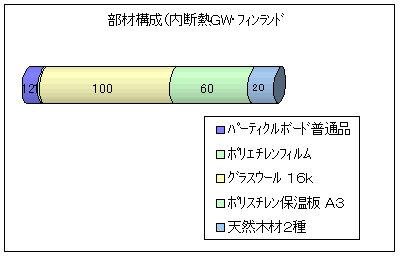
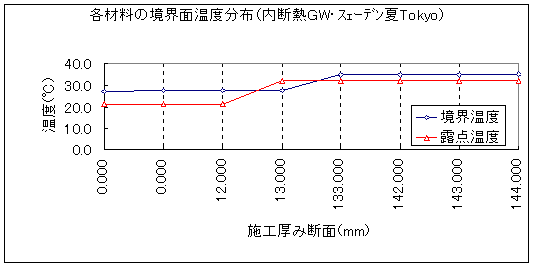
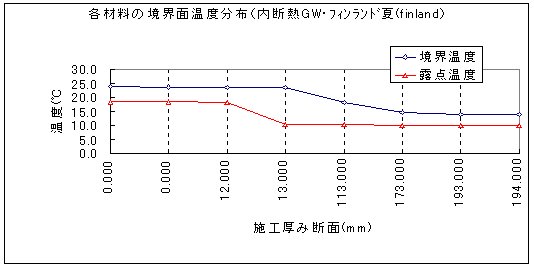
 このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は
このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は