 |
「内断熱工法・結露グラフ冬」
「外断熱工法・結露グラフ冬」
「内断熱工法・結露グラフ夏」
「外断熱工法・結露グラフ夏」
| |
| |
| |
◆ 健康と住まい−36◆◆◆
◆◆
◆◆◆
◆◆◆◆ present by apss
朽木 醒(くちき あきら)と申します。
健康と住まいの36回目になりました。
36・「住まい」の結露と断熱材を科学する
☆ 前回は、住宅の完成後不安を抱えているメールについて述べましたが、
☆再度お知らせ・ハウスメーカーや工務店に設計施工で注文の方の為に、
施工時の「自主・撮影検査マニアル」の無償・提供をしています。
以下をクリックすると、
「写真撮影検査マニアル」をダウンロードできるサイトになります。
クリックが出来ない場合は、アドレスをお使い下さい。
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/sannsya/sannsya1.html#J
「写真撮影検査マニアル」サイト
☆ 建物にとっては、換気が大切なのですが、断熱も切り離せない関係にあります。
今回は、断熱材と結露に付いての科学的考察です。
☆01 断熱はなぜ必要なのか?
省エネルギーが問題になるようになってから、断熱材は発達してきました。
それ以前の断熱は、断熱を意図した材料ではなく、壁や屋根、床等の材料に、
断熱性能があった、と言うことで、積極的に断熱材として、
使われていたわけではありません。
したがって、断熱工法と断熱材は、空調と共に発達してきたのであり、
空調のエネルギーを効率よくし、無駄に熱をロスしないために必要な部材なのです。
断熱材料は過去50年位の間に発達してきたもので、この間技術の発達も著しく、
様々な材料が開発されてきたのです。
グラスウール(ガラス繊維系)を筆頭に、ロックウールのような鉱物繊維系、
ウレタンやポリスチレン、フェノールフォームなどの発泡樹脂系、
セルロースファイバーのような紙質繊維系、珪酸カルシュウム発泡系、ウール繊維系や
コルクを使った自然素材のものまで、本当に多様になってきました。
材料の多様性に加えて、使い方も多くの工法が考えられ、
従来からのコンクリートの内断熱、木造の充填断熱(内断熱と表記すること有、
本編ではこちらを主に内断熱とします)、コンクリートの外断熱、
木造の外張断熱(本編では主にこれを外断熱と表記)、
木造の柱内の一部に取り付ける充填外側断熱、
鉄骨構造の構造面内に取り付ける壁内充填断熱等々、
住宅の工法との兼ね合いで、様々な使い方が開発されています。
空調の使用が日常化し、数百種以上も有る多様な工法の中で、快適に過ごすため、
断熱材が必ず必要になったのですが、結露やカビ、ダニ、腐朽菌、シロアリ等の、
被害をまねく原因にもなるのが断熱材の難しいところであり、
それぞれの断熱材の個性を生した工法でないと、安心できないのもまた真実です。
☆02 断熱材の特性を生かした使い方を考える。
断熱材が快適住宅や健康住宅の決め手の1つになったように、言われて久しのですが、
また、各工法の技術者は、それぞれが使っている断熱材が、
その住宅にとって最も良いと、主張しています。
しかし、科学的根拠に基づいて、決め方を示している工法は見たことがありません。
ただ漠然と、断熱材が示されているか、物性や個別の性能が、
記されているものが多く、比較検討された過程は判りません。
このような、状況にあるのが現在の「住まい」の断熱材なのですが、
どの断熱材が、皆さんの建てることを望む建物に、本当に適合しているのか、
判断に苦しむことになるのは当然のことです。
今回は、断熱材を科学的に考察し方向性を示しますので、建てたい工法に、
どの断熱材が適しているのか、この考察を参考にして欲しいのです。
☆03 内断熱・冬の結露
さて、下の図を見てください。内断熱(充填断熱)、外断熱(外張断熱)の、
結露発生の可能性を示す、グラフと壁部材の構成仕様になります。
このグラフで赤線は透湿係数による部材境界の露点温度を、
青線は断熱抵抗による部材境界での温度そのものを示しています。
したがって、この赤線と青線が交差すると、
その部分が結露の可能性の高い状態になっていることを示します。
温度・湿度の前提条件は特記のない場合は、東京の冬を想定し、
室内は22℃湿度60%と仮定しています。
また、夏は室内で27℃湿度70%と仮定しています。
外気は冬:最低気温平均・湿度平均、夏:最高気温平均・湿度平均
(下記をクリックすると「内断熱工法・結露グラフ冬」が出ます。)
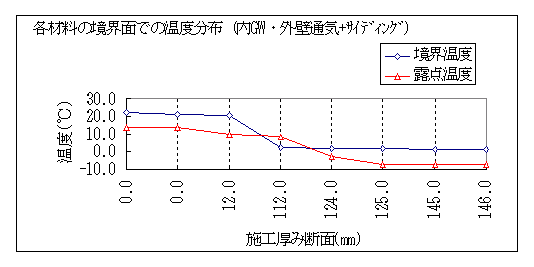
図−Uchi1:内断熱グラスウール冬・結露推定グラフ
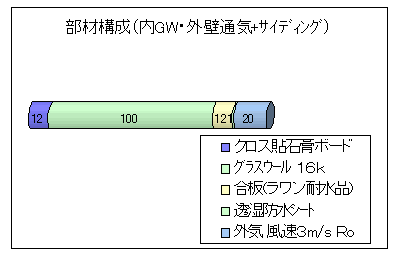
図−Uchi2:内断熱グラスウール冬・壁部材構成
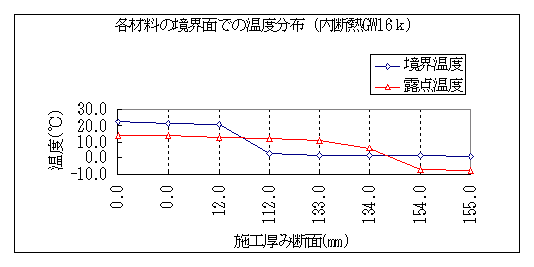
図−Uchi3:内断熱グラスウール冬外壁モルタル・結露推定グラフ
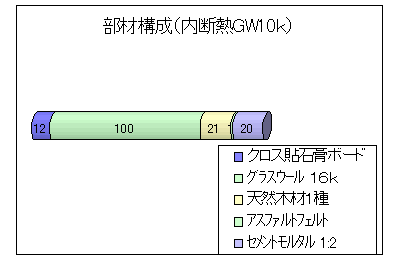
図−Uchi4:内断熱グラスウール冬外壁モルタル・壁部材構成
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/meru/kenmeru35.html#uchidannnetu1
☆3-1 内断熱は壁内結露の可能性が高い
図−Uchi1はグラスウール100mm厚(GW)使用の内断熱(充填断熱)で、
外部通気があり、外壁材はサイディングとした場合です。
グラスウールと合板の境界で露点温度が境界温度を超えてしまい、
結露可能性大の状態になります。
このGWの厚さが50mmに減っても、この状態はほとんど変わりません。
もう一つ、内断熱に良く使われる外壁材として、モルタル塗吹付タイル仕上がありますが、
図−Uchi3に示されているように、外壁通気+サイディング工法より、
もっと結露しやすく、危険な状態になっています。
これらのグラフで判るように、壁内部にグラスウールを使った、
内断熱工法では、壁の内部に結露するのが当然なのです。
これは、グラスウールの断熱抵抗と透湿抵抗のバランスが悪く、
断熱抵抗は良いのですが、透湿抵抗は無いに等しい性能ですので、
温度は下げることが可能であっても、
湿度(水蒸気)を下げることが出来ないのです。
したがって、グラスウールの内部が露点温度以下の状態になり、
結露が始まることになります。
この状況を改善する為に、外壁通気工法が開発され、
合板を介してでも水蒸気を外に排出し、外壁通気より放散させる工法が、
外壁通気工法なのですが、モルタル塗の外壁よりかなり改善されていますが、
図−Uchi1で示した通り、外壁通気を確保している壁でも、
グラスウール内では結露が起きているのが現状です。
但し、東京では冬でも、日中は10℃以上に気温が上昇する日も多く、
結露水の蒸発も起こる為、被害に遇わない「住まい」も沢山あります。
以前に北海道で起こった、「なみだ茸事件」はこの壁内結露を象徴する事件だったのです。
☆04 外断熱冬の結露
一方外断熱にすると、どうなるのでしょうか?
図−Soto1は、同じくグラスウールウールを外断熱に使い、
その性能を内断熱と比べてみたものですが、同じGWでも外断熱としてつかうと、
とても良好な断熱性能を示し、結露の恐れは全くありません。
内断熱と外断熱では、これほどの性能と効果が違ってくるのです。
(下記をクリックすると「外断熱工法・結露グラフ冬」が出ます。)
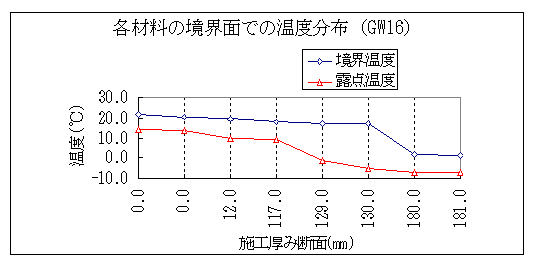
図−Soto1:外断熱グラスウール冬・結露推定グラフ
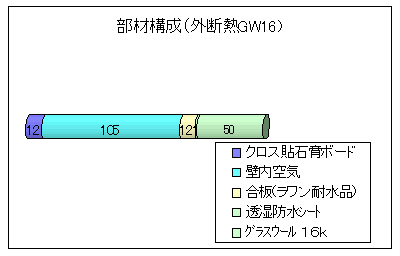
図−Soto2:外断熱グラスウール冬・壁部材構成
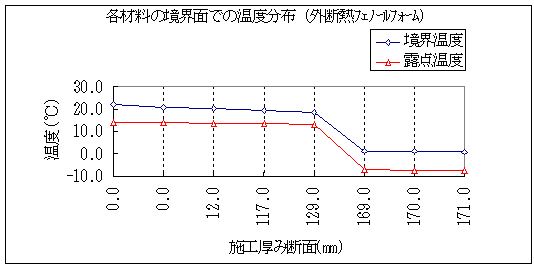
図−Soto3:外断熱フェノールフォーム冬・結露推定グラフ
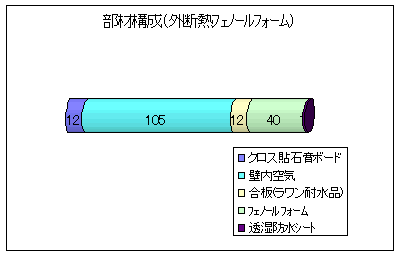
図−Soto4:外断熱フェノールフォーム冬・壁部材構成
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/meru/kenmeru35.html#sotodannnetu1
それでは、GWを使い外断熱にすれば良いのではないかとの、
発想が生まれてきますが、そう簡単には解決できないのが、断熱の問題なのです。
GWを外に使う場合には、外壁の取り付けの問題を解決しなくてはなりません。
外壁は重量があるので、しっかりとした下地が必要となりますが、
GWの場合断熱効果の関係で100mmは必要になり、外壁通気を取ると、
仕上部材の厚さも含め、躯体外面より135mmは最低でも必要になります。
この空間を強度的に丈夫な下地とすると費用も大変ですし、
下地部分は断熱材が付けられないので、ヒートブリッジ(断熱の隙間)となり、
外断熱の効果が発揮できなくなるのです。
北欧ではコンクリートの外壁に、グラスウールを使い断熱していますが、
下地や防水処理、窓周り等の開口部の納まりなど、かなりの費用負担がありますが、
下地や納まりの為の、システムが出来上がっていますので、
規模のある集合住宅などでは、スタンダードな仕様となっているのです。
我が国の現状では、外断熱の認知度が低くシステムが出来ていませんので、
個別住宅で取り入れようとすると、費用は北欧の倍以上も必要になります。
図−Soto3は、外断熱で断熱材としてフェノールフォーム(樹脂系発泡断熱材)
を使用した場合の、結露の有無を示す、折れ線グラフです。
非常に綺麗な平行線を示しており、断熱抵抗と透湿抵抗のバランスがよく、
結露の心配が全くありません。
フェノールフォームと言う断熱材は、前記のGW100mmと同等程度の、
断熱効果を発揮するのに、40mmの厚さで可能になるので、
壁内通気や外壁のサイディングを含めても75mm程度で済み、
特殊な釘を使えば施工が可能です。
費用も少し高くはなりますが、手が届かないほど高価になることもありません。
☆05 内断熱夏の結露
夏の場合はどうなるのか
図-Uchi5、図-Uchi7は内断熱材グラスウールの夏の場合の折線グラフですが、
夏は外壁材に関係なく、また、外壁通気の有無にも関わらず、
結露の心配はないことを示しています。
夏に結露は関係ないと思う方が多くいますが、冷房を日常的に使う昨今は、
夏場にも壁の中に逆転結露(冷房に因り室内の壁が冷やされ、壁内に起こる結露)
が起こる場合があり、この結露にも注意しなければならないのです。
夏の逆転結露については、奥の深い問題がありますので、
次回に、詳しく説明します。
(下記をクリックすると「内断熱工法・結露グラフ夏」が出ます。)
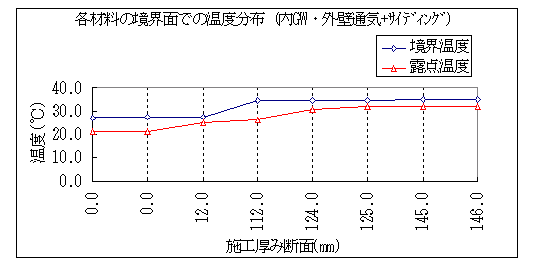
図−Uchi5:内断熱グラスウール夏・結露推定グラフ
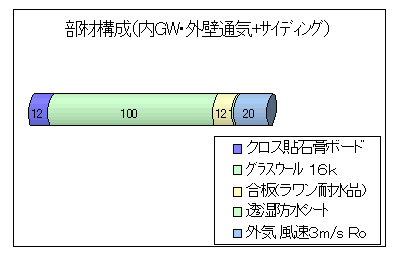
図−Uchi6:内断熱グラスウール夏・結露推定グラフ
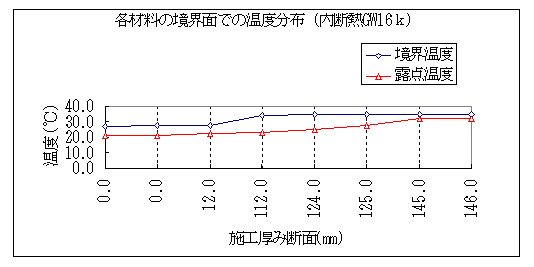
図−Uchi7:内断熱グラスウール夏外壁モルタル・結露推定グラフ
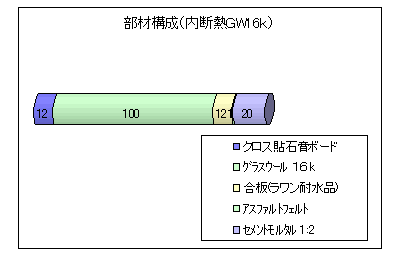
図−Uchi8:内断熱グラスウール夏外壁モルタル・壁部材構成
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/meru/kenmeru35.html#uchidannnetu2
☆06 外断熱夏の逆転結露
図−Soto5を見てみますと、、外断熱でグラスウールウール(GW)を使った際に、
結露の可能性があることを示す結果となっています。
これが、夏の逆転結露現象を示す、一つの例です。
外断熱では結露の問題は無かった仕様でも、夏になって冷房を使うと、
壁の中に結露の可能性が出てくることがあり、この状況を「夏の逆転結露」現象と、
表現しているのです。(次回に詳しく説明します。)
外断熱ならば、全てが良い訳ではない事が、お解りになると思いますが、
この理由は断熱材の断熱性と、透湿性のバランスにあるのです。
(下記をクリックすると「外断熱工法・結露グラフ夏」が出ます。)
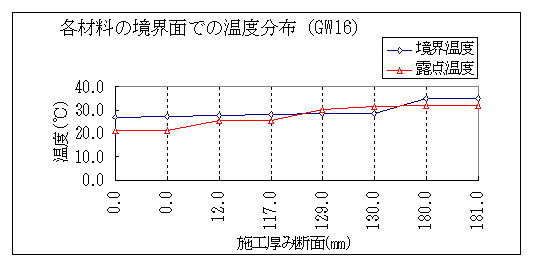
図−Soto5:外断熱グラスウール夏・結露推定グラフ
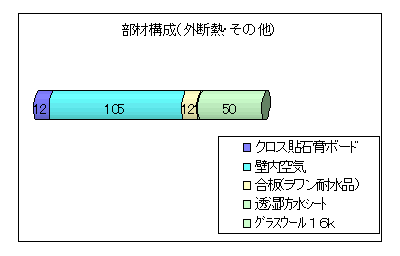
図−Soto6:外断熱グラスウール夏・壁部材構成
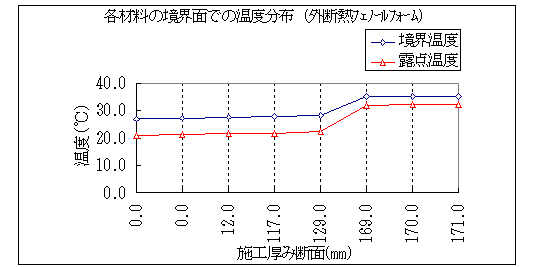
図−Soto7:外断熱フェノールフォーム夏・結露推定グラフ
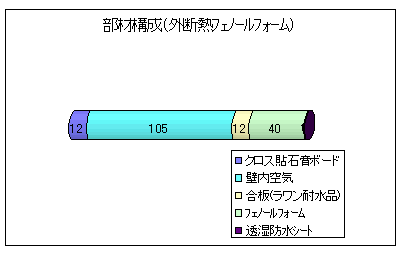
図−Soto8:外断熱フェノールフォーム夏・壁部材構成
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/meru/kenmeru35.html#sotodannnetu2
断熱抵抗と透湿抵抗の理論的考え方と「夏の逆転結露」の件は次回に廻しますが、
バランスを欠いた使い方をすると、外断熱でも結露の可能性があるのです。
図−Soto7は、フェノールフォームでの外断熱工法の夏の状況を示した、
折線グラフですが、冬同様に部材のバランスの良さが示されており、
綺麗な平行線の形を示しているのが判るはずです。
フェノールフォームのように、断熱抵抗と透湿抵抗が、
程よくバランスしている場合には、室内から外部までの部材で、
冬、夏共に問題はないのですが、グラスウールのように、
断熱抵抗と透湿抵抗との抵抗値が極端に違い、バランスを欠く断熱材を、
使う場合は、使い方に注意が必要なのです。
北欧では、コンクリートの外断熱や木造住宅の内断熱材にもグラスウールを使い、
十分な効果を上げ結露も起こしていませんが、それは建築物理の研究成果もあり、
使い方を熟知しているから出来ることなのです。
北欧の断熱材の使い方についても、次回以降に取り上げます。
続きは次回になります。
「外断熱スパイラルエアーシステム住宅」のページです。
apssのhp参考にしてください。
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/kennkou1.html
ありがとうございました。
 このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は
このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は
apss設計までをお願いします。


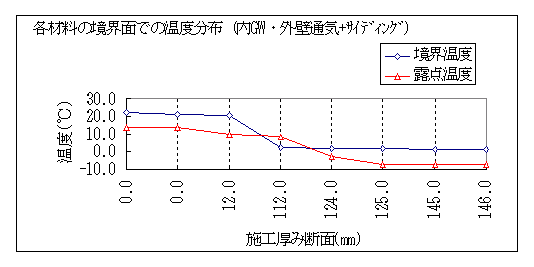
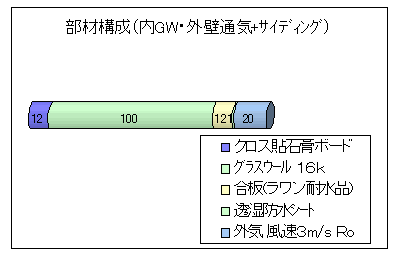
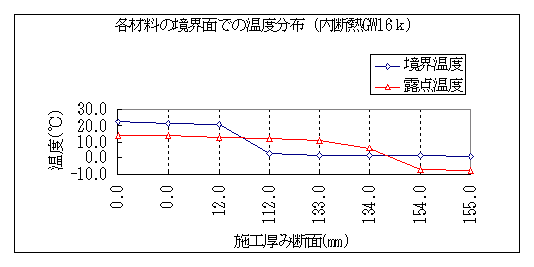
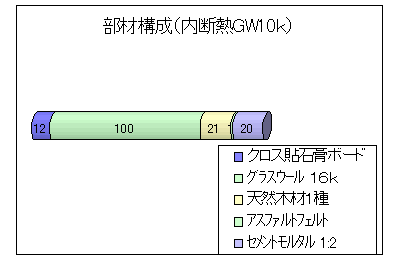
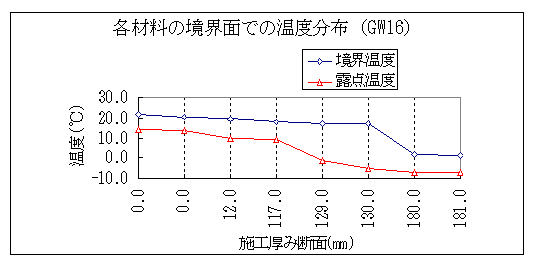
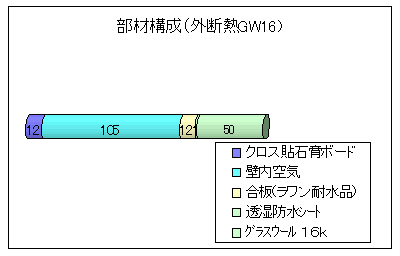
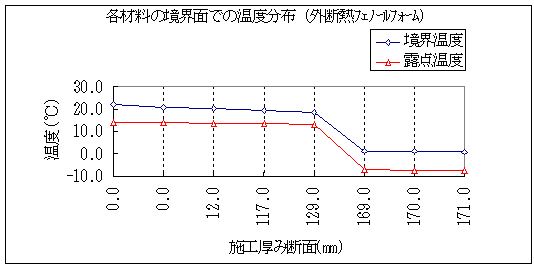
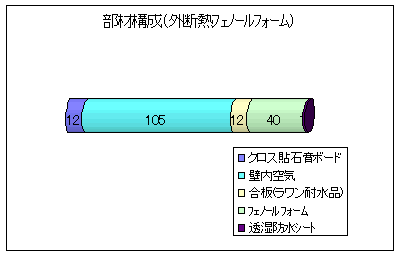
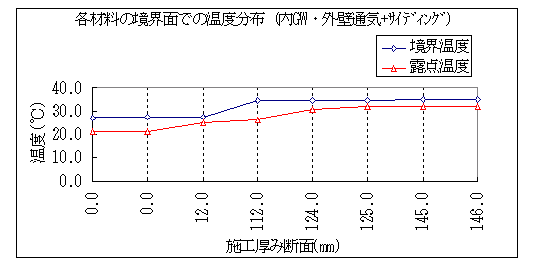
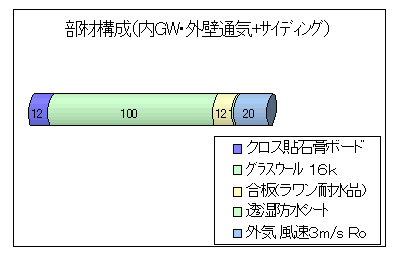
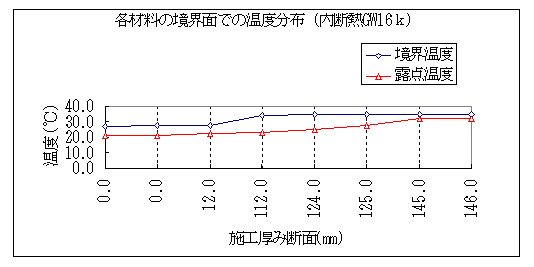
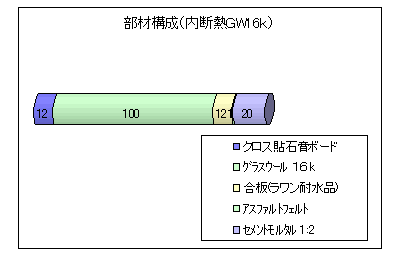
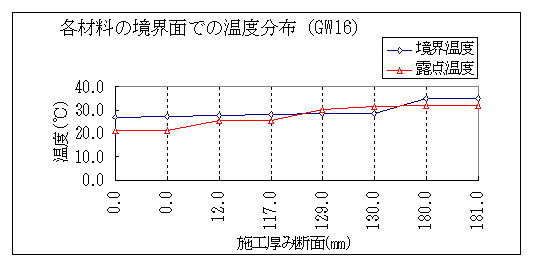
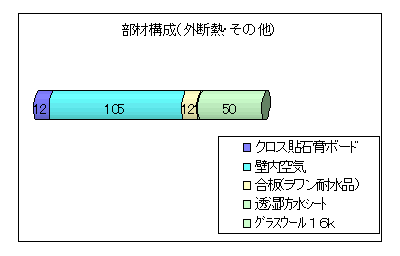
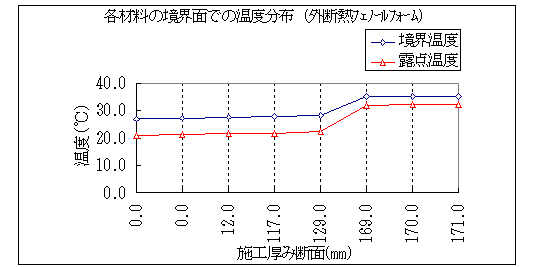
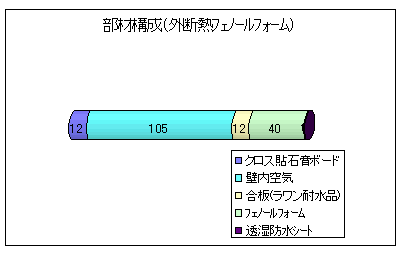
 このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は
このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は