 |
「図1:外断熱住宅換気概念図」
「図2:内断熱住宅換気概念図」
| |
| |
| |
◆ 健康と住まい−34 ◆◆◆
◆◆
◆◆◆
◆◆◆◆ present by apss
朽木 醒(くちき あきら)と申します。
健康と住まいの34回目になりました。
34・主な換気と断熱方法を解明する
前回は24時間強制換気が建築基準法で取り入れられたため、熱の放出も伴うが、
必要な換気は住み手の健康や、シックハウスの予防に役立ち、
ある程度の熱のロスは避けられないのであり、
特段の高気密はそれほど必要でないことを述べました。
今回は、沢山ある工法で、主に外断熱方式の「住まい」での換気方法について、
話をしてゆきたいと思います。
換気の最大の問題点は、壁の中の空気をどのように扱い、
どの様な換気法を取るかなのです。
室内空気や台所、浴室、WC等の換気は、前記した24時間換気の義務付により、
問題点を残しながらも、前進しており、換気の重要性を認識している工務店や
設計事務所、ハウスメーカーなどではそれほど差の無いシステムを、
取り付けるようになってきています。
注意しなくてはいけないのは、換気の重要性を担当者が認識しているか
どうかですが、この点はチェックする必要があります。
当MMの知識も役に立ちますので、担当者にぶつけてみた反応でチェックする、
こともできます。
室内換気の詳細などは、また後で話すことに致しますが、壁の中の空気の扱いは、
ほとんどの工法で、手を付けていないのが現状です。
床下や小屋裏の空気を、自然換気方式で換気している工法は沢山ありますが、
壁の中の空気は、なりゆき任せになっているのです。
神社仏閣や藁葺住宅等1925年以前の建物は、外気と室内空気が同質で壁も土壁、
柱は外気にいつも触れてることを、何度か記述しましたが、住宅技術が発達し、
壁の中に空洞が出来、暖冷房をすることで外気と室内空気が違ってきたので、
柱周りの空気はどちらともつかない空気になってしまったのです。
誰もが気持ちの良い生活を出来るようになることは良いことですので、
暖冷房することは当然のなりゆきですが、その時の換気の方法が問題になります。
以前のように自然の通気があれば良いと言う事にはなりません。
暖冷房を効率よくするために、断熱と気密化を壁の中にしてきたために、
壁の中は自然の通気が上手く出来ない環境になっていたり、
外気を導入することで、余計に壁内結露を促す場合が多くなったからなのです。
現在の住宅では、壁の中にほとんどの柱が隠されています。
柱は住宅の要であることは、誰でもが承知していると思いますが、
この柱の健康を考えていないのが、今日のほとんどの工法なのです。
木造住宅の耐久性を考えた場合、人が暖冷房を使うのであれば、
躯体(構造体)にも暖冷房のおすそ分けすることが、躯体も健康になる秘訣です。
断熱材や気密材等を使用したとしても、壁の中を内だか外だか判らない
場所にしておくと、結露やカビ、シロアリ、腐朽菌などの問題が発生するのです。
壁の中だけではありません、床下や天井裏、小屋裏等も当然外気か室内空気かの
どちらかにしなければ同様に、結露やカビ、シロアリ、腐朽菌などの問題が、
発生することになります。
したがって、暖冷房を使う住宅では、 床下や天井裏、小屋裏、壁の中も、
室内気で通気や換気を行わなければ、問題が発生する可能性が高くなるのです。
それでは、最近の一般的外断熱(外張断熱とも言います)住宅の換気を考えます。
(下記をクリックすると「図1:外断熱住宅換気概念図」が見えます。)
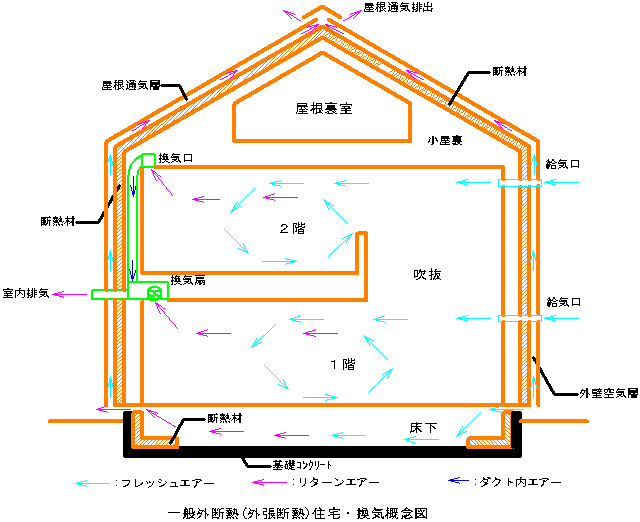
図1:外断熱住宅換気概念図 |
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/meru/kenmeru34.html#soto1zu
「 図1:外断熱住宅換気概念図」を見てもらえば判るように、
床下は自然換気が主体であり、
基礎部分に床下換気口を開け自然の風や温度差で換気をします。
一部に床下のみの強制換気を付ける工法もあります。
居室部分は、数室を一台で換気する、マルチ換気扇による換気で、
排出空気を外に直接放出しています。
換気方式としては、WC、脱衣、浴室からの換気で、
全ての部屋の換気をまかなう場合と、各室それぞれ別に給気口と排気口を設けて、
換気する方式があります。
給気法は、給気口を居室に設置し、機械排気による気圧の低下で吸気をする、
第3種換気方式を採用しているのがほとんどです。
熱交換器を使った強制給排気を採用している、工法もありますが、
電気代、フィルターの交換手間、熱交換率の問題等で、
あまり多くありません。
一般に外断熱方式の住宅は断熱性と気密性が良く、省エネ住宅と言われ、
その省エネ性を競い、空調のランニングコストが安いことを特徴としています。
しかし、今までは省エネ性を作り出す要素として、
気密性が大きく貢献していたのですが、24時間換気の導入により、
前述のように、ある程度の熱ロスは必要になりました。
熱交換型の換気扇を使用した場合、省エネの観点から、効率、電気代、
イニシャルコストを含めて比較すると、それほど大きな価値とは言えませんし、
かえって、フィルターの交換が疎かになると、空気の質が悪くなり、
健康等にマイナスになることもあります。
外断熱住宅の換気でも床下や小屋裏、壁の中になると室内空気を使用する工法は、
ほとんどありません。
理由はいくつもありますが、主なものは、省エネから考えると、
床下や小屋裏、壁の中を機械換気するのは省エネにならない、
自然の通気で換気するのが昔からの流れである、
壁中換気の重要性が認識されていない、の3点に集約できます。
この3点について、もう少し話を進めてゆきたいと思うのですが、
その前に、内断熱(充填断熱と言われる)の換気方法も見てみましょう。
(下記をクリックすると「図2:内断熱住宅換気概念図」が見えます。)
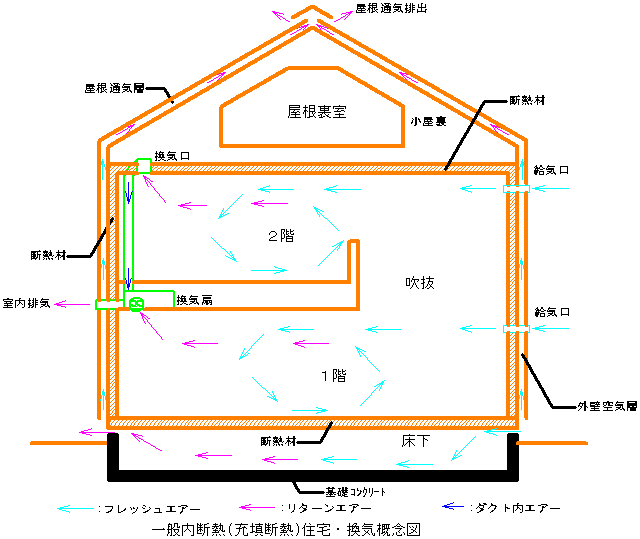
図2:内断熱住宅換気概念図 |
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/meru/kenmeru34.html#uchi2zu
「図2:内断熱住宅換気概念図」に、
一般的な内断熱の換気方式の概要を示してあります。
この図でも判る通り、小屋裏と床下は自然換気(機械換気使用工法も有)
が普通の換気方法となっており、壁の中は断熱材が充填されるため、
ほとんど通気スペースが無く、換気を考える余地を無くしてしまっているのです。
この状況で、高気密や高断熱にしようとすると、さらに断熱材を詰め込んで、
断熱性能を上げ、気密シート(ビニールシート)を張ることになります。
人の環境と省エネのためとの考えで、このような工法を取り入れたのですが、
実際には、壁中の通気が無くなり住宅の躯体の健康を損なう工法になってしまい、
住宅の耐久性を損なうのですから、長い目でみるとちっとも省エネには、
貢献していないのです。
室内空気を小屋裏や床下、ましてや壁中に回すのは難しく、
小屋裏や床下、壁中は内部とも外部ともつかない、
中途半端な部分になっていても、不思議に思わなくなってしまったのです。
そのため、この中途半端な部分の健康(耐久性)をおざなりにし、
木造の寿命は30年との、もっともらしい論理が出来上がってしまったのです。
木造の寿命30年には、もう少し肉付けがあり、火事や地震が頻繁に起きたのも、
この論理の隙間を埋めていました。
昔は、火事や地震が30年程度では起こるので、その程度の耐久性があれば、
木造は良いのだとの考えが押し付けられていたのですが、耐震性、耐火性とも
向上してきた現在は、木造でももっと耐久性があるはずだと言われ出したのです。
しかし前述したように、建物躯体の耐久性向上には、
躯体に対する換気や通風が欠かせません。
躯体に対する換気や通風を確保するためには、小屋裏、床下、壁中を
連続して通る換気が必要となり、これらの通風換気は全てが、
室内空気でおこなえる、室内扱いとして計画するしかないのです。
続きは次回になります。
今回はここまでです。
次回は、健康な空間についてです。
「外断熱スパイラルエアーシステム住宅」のページです。
apssのhp参考にしてください。
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/kennkou1.html
ありがとうございました。
 このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は
このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は
apss設計までをお願いします。


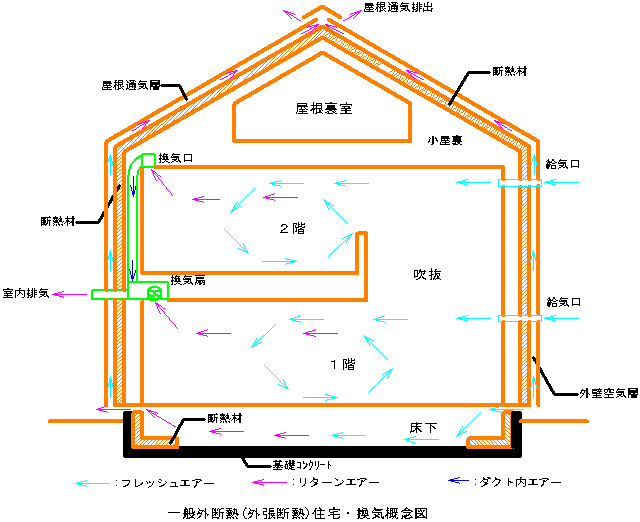
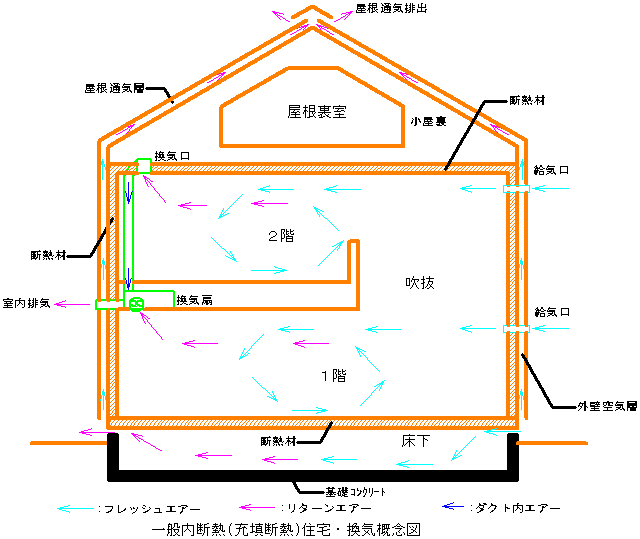
 このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は
このサイトについて、ご意見、ご感想、ご質問等は